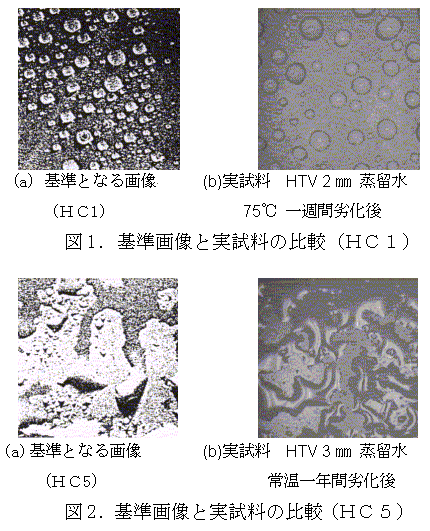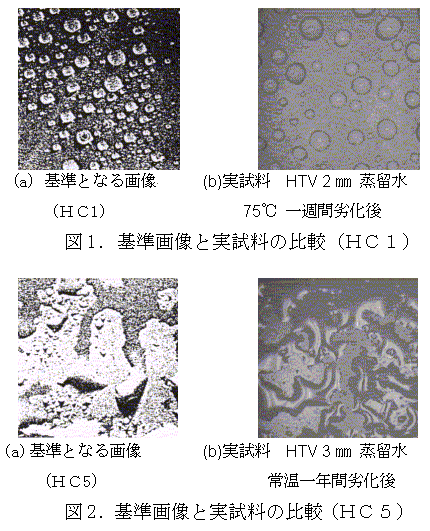
電気絶縁材料の接触角の画像解析に関する研究
05E19 中田 宏明
1.はじめに 屋外用がいしなどの初期表面劣化過程の指標の1つとして、試料表面の撥水性の低下が観測されている。現在、一般的には誘電性試料の撥水性の低下の診断を、接触角の測定だけに頼っている。しかし、接触角はミクロな領域の撥水性を測定しており、試料表面全体の撥水性を必ずしも示していない。これに対し、STRI法を用いた表面劣化診断法は、試料表面全体の撥水性を水滴付着状態として観測することができる。本研究では、この表面劣化診断に画像解析を用いることで、目で見ることにより測定する場合の、測定者の主観による誤差のない、測定の高度化と高速化を目指した。
2,画像解析結果及び考察 表面劣化診断に、画像解析を用いるため、まず、画像解析ソフトをダウンロードし、そのソフトの表面劣化診断への適応性について検討した。本研究では、以下に述べる3つの画像解析ソフトをダウンロードした。1つ目は、bmobe Ver1.0.0であるが、このソフトはロース検出用であり撥水性の評価への適応性には欠けていた。2つ目は、Lia32 For Windows95である。このソフトも葉面積推定、色解析用ソフトであることから、撥水性の評価への適応性には欠けていた。3つ目のNIHImageは、広範囲な用途に対応した画像解析ソフトであり、今回の研究に対しても十分な対応性を持っていた。従って本研究には、NIHImageを用いた。なお、本ソフトのWindows版では、処理後の画像保存が出来ないなどの欠点がある。また、表面劣化診断法としては、STRI法を用いた。本研究では、まず、STRI法を用いるにあたり、その基準となるHC1〜HC6までのサンプル画像についての測定を行った。サンプル画像に対して、様々な処理を行うことで、撥水性を評価するのに適したパラメータ及び測定結果の信頼度を上げるための処理手順についての検討を行った。
今回は、主な画像計測の対象として、水滴の占める総面積と、水滴の数を用いて画像処理や測定を行った。その際、画像内の不均一な光源の効果の除去が非常に大きな課題となった。この課題を解消するために、閾値化処理、背景の除去、スムージングなどの処理を行ったが、今回は実際にHCレベルを評価できるまでの処理系の構築はできなかった。
次に、実試料に対して、画像処理を用いた撥水性の評価の検討を行った。一週間程度水浸劣化させた実試料は、STRI法によれば、最も撥水性の良いクラスであるHC1に属すると判断される。基準となる画像との比較を図.1に示す。また、昨年2月より約1年間水浸劣化させた試料の撥水性レベルは、HC5またはHC6程度に属するものと思われる。基準となる画像との比較を図.2に示す。これらに対する画像処理によるHCレベル評価は、水滴抽出が完全にはできなかったため行えなかった。
3.まとめ 今回の研究では、背景除去と対象物の抽出処理が完成できず、画像処理を用いた表面劣化診断用の測定系の確立までに至らなかった。特に、今回の解析では、STRI法のHC2〜HC5の区別が困難であった。
実試料の撥水性に関しては、接触角の測定は撥水性低下の初期過程に対して有効であり、STRI法はより劣化の進んだ状態の判断に有効であることが示唆された。