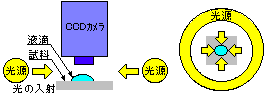
電気絶縁材料の撥水性の画像解析に関する研究
07E28 長谷川
公明
1.はじめに
シリコーンゴムは優れた電気的特性に加えて、高い表面撥水性を有しており、屋外用がいしとして広く用いられつつある。その初期表面劣化過程の一指標として、材料表面の撥水性低下を観測することは非常に有用である。本研究では従来行われている接触角の測定とSTRI法を基にした撥水画像解析による、撥水レベル(HC)の自働診断を目指して研究を進めた。2.実験方法
HTVシリコーンとEPDMの2種類のゴム試料を用い、それらの吸水劣化および乾燥回復過程における試料重量,静止接触角,撥水性画像をそれぞれ測定した。撥水性画像は水平に置いた試料表面に蒸留水を噴霧し、鉛直方向よりCCDカメラで撮影した。画像データはNIHImageにより画像解析し、水滴面積の大きさ分布および水滴の真円度についての計測を行った。実験は試料(HTV,EPDM)の水浸劣化過程(75℃・98℃)と、乾燥回復過程(75℃・98℃)、ヘキサン浸(40℃)、ヘキサン浸後の乾燥(40℃)の各行程を組み合わせて行った。また、画像解析用の試料面の水滴の照明方法についても検討した。3.実験結果および考察
接触角の測定結果より、水浸過程では基本的にどの試料であっても接触角は低下した。逆に乾燥過程では基本的にすべての試料で接触角は回復した。接触角の変化の原因は、水浸過程では試料表面近くの低分子量油分(LMW)が溶出し、水が吸収されたためである。これらにより試料の表面エネルギーが上がり、接触角が低下した。LMWの溶出は撥水性を低下させるが、水分の蒸発は逆に回復させる。4.まとめ
本研究により正確な撥水性の画像診断を行える様になった。今後,HCレベル分けに必要な定量的基準を画像解析指標から見出し、画像処理結果からのHCレベルの自動判断を行える様、画像解析ソフトの改良が望まれる。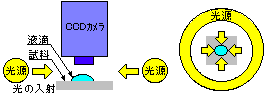
図1.照明環境設定
(a)
照明設定 (b)光源と試料の位置表1.微小範囲
(約1mm2)の撥水性診断 (HTV)| 噴霧液の表面張力[mN/m] |
乾燥後 |
水浸後 |
||
|
72.8 |
55 |
72.8 |
55 |
|
|
大きさ[pixel] |
464 |
3768 |
14058 |
19933 |
|
真円度[%] |
87 |
57 |
77 |
46 |