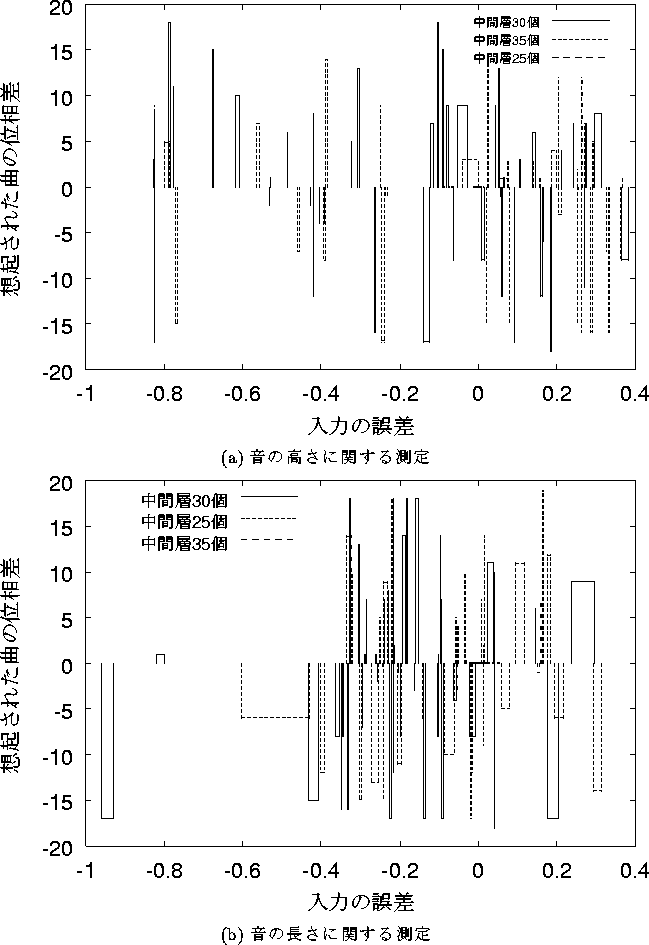
図 6.11: 中間層の違いによる誤差の許容(内部記憶層30個固定)
学習が成功した場合のネットワークの結合荷重及び内部記憶層の値を使用して, 教師信号の第1音のみを与えて想起実験を行なった. その結果ネットワークが出力した値は教師信号のものと全く同じになり, 正しく学習・想起が行なわれているといえる.
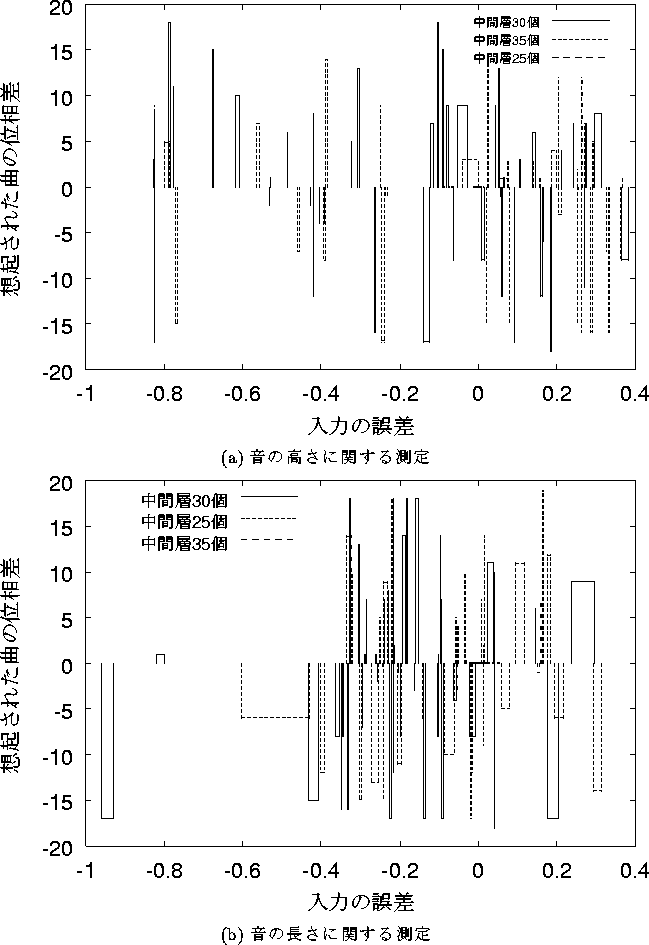
図 6.11: 中間層の違いによる誤差の許容(内部記憶層30個固定)
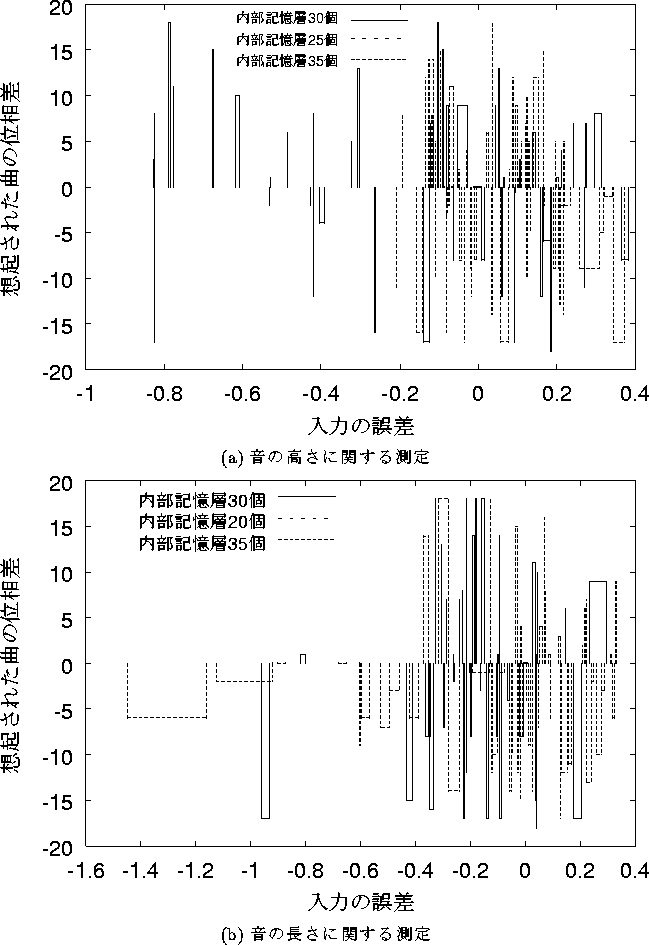
図 6.12: 内部記憶層の違いによる誤差の許容(中間層30個固定)
また与える信号に誤差を加えてネットワークに入力して想起を行なわせた. その結果,音の高さでは図 6.11 (a), 6.12 (a) 音の長さでは図 6.11 (b), 6.12 (b)のようになり, 与える信号によっては正しい入力をしなくても想起が成功している. 横軸に入力に対する誤差の大きさ, 縦軸に想起された曲が教師信号とどれだけずれているかを表している. 教師信号は全部で38音あるので位相のずれは-18音から+19音までとする. 図中に値がない部分は想起が失敗している箇所である. この結果より中間層が一定であれば内部記憶層の素子数が多い方が 入力誤差に対する許容が大きくなることがわかる. これは想起を行なう際に入力が間違っていても, 教師信号に基づいた内部記憶層からの入力が多数あるので その情報から教師信号の情報を復帰させることができるからであると思われる. しかし,多数あるとしても入力のパターンが異なっているために 最初の音であるとは判別できず位相差を生じていると考えられる. また内部記憶層の素子数が一定であれば中間層の素子数が多い方が許容が大きくなる. 即ち内部記憶層の素子数が中間層の素子数より多ければ, 入力信号に誤差が含まれていても教師信号を再現することができるといえる.
中間層,内部記憶層の素子数をさらに増加させると, 想起過程の初期段階で内部記憶層に入力する値を ランダムな値や全て0にするなどの条件下でも 遅れを生じるだけとなった.