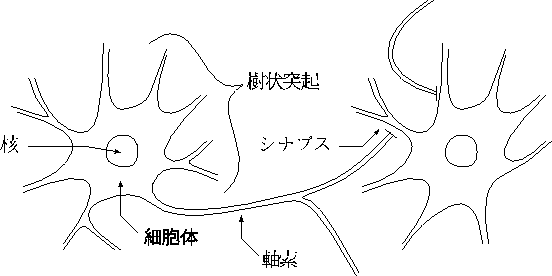
図 2.1: ニューロンの構造
生体の神経細胞は、一般に図 2.1 のように表わされ、主に細胞体、 樹状突起、軸索の三つの部分から成っている。細胞体の中ではタンパク質など細胞の 活動に必要な物質が合成されている。情報の線路である軸索は他の神経細胞へと 延びており、そこの樹状突起および細胞体へ付着する。この付着している部分を シナプスといっている。一般に、軸索は 10 ないし数百に枝分かれしてそれぞれ 他の細胞へとつながっており、また一つの細胞が受けるシナプス結合の数は 数百ないし数千あるいは数万にも及んでいる。
神経細胞は、細胞膜によってその内部が外液と隔てられている。そのため、膜の イオンチャンネルの働きによって内部と外部におけるイオン濃度に違いが生じ、 膜に電位差が生じている。この電位差を膜電位とよぶ。外部の電位を基準にしたときの 静止状態での細胞内部の膜電位はおよそ -70 [mV] であるが、 外部からの作用によってこれを -50 [mV] 程度に上げると、 細胞膜のイオン透過性に変化が起きる。そのため、膜電位が一時的に +20 [mV] 以上に上昇し、再び元に戻るという現象が 生じる。このことをニューロンが興奮した、あるいは発火したという。 膜電位の一時的な上昇すなわちインパルスは、はじめは膜の局所的な部分で発生するが、 やがて軸索にたどりつき、軸索にのって他の細胞へと伝搬するわけである。
軸索を通してやってきたインパルスはシナプス結合部分に到達するわけであるが、 ここでシナプスの性質には二種類あるため、インパルスはどちらかの働きに変わる。 一つは興奮性シナプスを通った場合であり、これによりニューロンを発火させやすく する作用に変わる。もう一つは抑制性シナプスを通った場合であり、逆にニューロンを 発火させにくくする作用に変わる。多くの細胞から軸索を通してやってきたインパルスに よるこれらの作用は合わせられ、総じてニューロンの発火の有無を決定するわけである。
ここで注目すべきことは、ニューロンが興奮して発生するインパルスは、興奮のさせ方に よらずほとんど同一の波形となっていることである。すなわち細胞の状態としては、 インパルスが発生するかしないかの二つの状態のみで、これを全か無かの法則という。 これにより、全となるか無であるかを決める外部からの作用には閾値があることが分かる。
インパルスの波形が入力によって変化しないことから、情報はインパルスの発生頻度に あると考えられている。この頻度の大小が信号の強弱を示すわけである。
その他に重要な性質として不応性がある。ニューロンが発火した直後からわずかな間は 続けて発火しにくくなる性質である。発火した直後には絶対不応期に入り、いくら 外部から刺激を与えても全く発火しなくなる。すこし時間が経つと相対不応期に入り、 発火はするものの閾値が高くなって発火しにくい状態になっている。このため、 インパルスの発生頻度には上限が存在する。